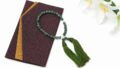“土用の丑の日”って結局なに? うなぎを食べる理由とは?
7月~8月頃になると、スーパーやコンビニに並ぶ「うなぎ」の文字。
でも、「丑の日ってなに?」「なぜ“うなぎ”限定?」と思ったことはありませんか?
この記事では、土用の丑の日の由来を歴史的に深掘りしながら、
現代の食文化や“うなぎ以外”の楽しみ方も紹介していきます!
「土用」と「丑の日」の意味を知る|古代暦と五行思想の名残
「土用」とは?
- 「土用(どよう)」は、中国の五行思想に由来する考え方。
- 一年は「木・火・土・金・水」の五行に分けられ、季節の変わり目(立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間)を「土」に割り当てた期間を「土用」と呼びます。
つまり、夏に限らず、年に4回“土用”はあるのです。
「丑の日」とは?
- 十二支(子・丑・寅…)は日付にも適用され、12日周期で巡ります。
- その中で、「土用」の期間にあたる「丑の日」が “土用の丑の日”!
例:2024年は7月24日(水)と8月5日(月)が該当(年によって1回or2回)
なぜ“うなぎ”を食べるようになったのか??諸説紹介?
平賀源内のアイデア説(最有力)
江戸時代、夏はうなぎが売れずに困っていたうなぎ屋が、博学で有名だった平賀源内に相談。
彼が「丑の日に“う”のつくものを食べると縁起が良い」として、
「本日、土用丑の日」と書いた看板を出したところ、大繁盛!
これが定着していったとされています。
「う」のつく食べ物を食べると夏バテしない説
もともと日本には、「丑の日に“う”のつくものを食べると体に良い」という民間信仰がありました。
- うなぎ(滋養強壮)
- うどん(消化が良くて涼しい)
- 梅干し(殺菌・熱中症予防)
- うり(夏野菜・水分補給)
この中でも、スタミナたっぷりの“うなぎ”が象徴的になったと考えられます。
春木屋善兵衛説(食文化起源)
別の説では、江戸の有名うなぎ店「春木屋善兵衛」が、
土用の時期にだけうなぎが傷まず売れたことから、
「この日が縁起が良い」と評判になったという話も。
どの説も、食文化×民間信仰×商業の知恵が重なってできたといえそうです。
うなぎだけじゃない!土用の“う”を楽しむ食文化
うなぎ以外にも、“う”のつく食材を楽しむのは立派な土用の風習!
| 食材 | 効能 | 備考 |
|---|---|---|
| うどん | 冷たくて喉ごしがよく、食欲不振のときに◎ | 「冷やしうどんの日」も近い時期に |
| 梅干し | クエン酸で疲労回復、抗菌作用 | 昔からお弁当の定番 |
| うり(キュウリ・スイカ・冬瓜など) | 水分補給&利尿作用で体を冷やす | 昔は「瓜(うり)」で“う”を補う風習も |
| 牛肉 | 高たんぱく、鉄分豊富で夏バテ防止 | 近年は「うなぎの代わり」に食べる人も |
最近では「う巻き(うなぎ入り卵焼き)」や「うなぎ風ナス料理」など、アレンジ土用グルメも注目されています。
現代の楽しみ方|うなぎ以外でも、夏のパワーチャージを!
- 価格が高騰しているうなぎですが、「無理して食べる」必要はありません。
- スーパーやコンビニでも、手軽な“う”のつく惣菜やお弁当が並ぶように。
- 外食でも「うな重」以外に「うどん」「牛丼」「夏野菜メニュー」など、多彩な選択肢が登場しています。
「“うなぎ以外”でもいい」と考えることで、誰でも気軽に“土用グルメ”を楽しめるようになってきているんです。
まとめ|土用の丑の日は、日本の“知恵と遊び心”が詰まった季節行事
土用の丑の日は、古代中国の思想、日本の民間信仰、江戸の商業文化が絶妙に混ざり合った、実にユニークな風習です。
- うなぎの滋養効果と「う」の語呂合わせ
- 平賀源内のアイデア力
- 「丑の日」の選び方と暦の知恵
すべてを知れば知るほど、“うなぎを食べるだけじゃない奥深さ”が見えてくるはず。
今年の土用の丑の日は、ちょっとだけ由来を思い出しながら、
日本らしい夏の楽しみを味わってみてはいかがでしょうか?