 お祭り
お祭り【葵祭】千年以上の伝統を誇る京都三大祭のひとつ
葵祭は、京都の賀茂御祖神社(下鴨神社)と賀茂別雷神社(上賀茂神社)で毎年5月15日に行われる由緒ある祭礼です。起源は6世紀にさかのぼり、平安貴族の装束を纏った華麗な行列が市中を練り歩きます。本記事では、葵祭の由来や歴史、見どころを詳しく解説し、観覧のポイントや周辺観光情報も紹介します。千年の伝統を体感できるこの特別な祭りを、ぜひ訪れてみてください。
 お祭り
お祭り 春の行事
春の行事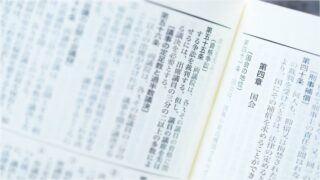 歴史にまつわる行事
歴史にまつわる行事 お祭り
お祭り 歴史にまつわる行事
歴史にまつわる行事 春の行事
春の行事 歴史にまつわる行事
歴史にまつわる行事 2月
2月 歴史にまつわる行事
歴史にまつわる行事 1月
1月