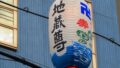夏の青森を彩る「青森ねぶた祭」は、毎年8月2日から7日にかけて開催され、国内外から多くの観光客を魅了しています。
巨大な灯籠「ねぶた」が街を練り歩き、跳人(ハネト)たちが「ラッセラー」の掛け声とともに踊る姿は圧巻です。
この祭りの起源や歴史、現代の様子について詳しく見ていきましょう。
行事の基本情報
- 行事名:青森ねぶた祭
- 開催時期:毎年8月2日~7日
- 主な開催地:青森県青森市
- 主な見どころ:大型ねぶたの運行、跳人の踊り、ねぶた海上運行、花火大会
青森ねぶた祭の由来と歴史
青森ねぶた祭の起源は明確ではありませんが、奈良時代に中国から伝わった七夕祭りの灯籠流しと、津軽地方の「眠り流し」と呼ばれる風習が融合して生まれたとされています。
「眠り流し」は、夏の農作業で溜まった疲れや眠気を払うために行われた行事で、これが「ねぶた」という名称の由来とも言われています。
また、七夕祭りでは、穢れを川や海に流す禊の行事として灯籠を流して無病息災を祈りました。
これが「ねぶた流し」となり、現在のねぶた祭の海上運行に繋がっています。
現代の青森ねぶた祭の様子
現在の青森ねぶた祭は、毎年8月2日から7日にかけて開催され、期間中は大型ねぶたが市内を練り歩きます。
跳人(ハネト)と呼ばれる踊り手たちが「ラッセラー、ラッセラー」の掛け声とともに踊り、祭りを盛り上げます。
最終日には、受賞したねぶたが海上を運行し、花火大会とともに祭りのフィナーレを飾ります。
まとめ
青森ねぶた祭は、奈良時代の七夕祭りや津軽地方の「眠り流し」といった風習が融合して生まれた、歴史ある祭りです。
現代では、巨大なねぶたと跳人の踊りが特徴的な、青森の夏を代表するイベントとなっています。
その由来や歴史を知ることで、祭りの魅力をより深く感じることができるでしょう。
- 青森ねぶた祭 オフィシャルサイト (ねぶたの由来 – ねぶたを知る | 青森ねぶた祭 オフィシャルサイト)