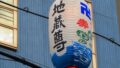夏の夜、櫓を囲んで太鼓と囃子に合わせ輪になって踊る――そんな風景は日本の夏の原風景と言えるでしょう。
しかし、この「盆踊り」はどこで生まれ、どのように全国へ広がったのでしょうか。
本記事では平安末期の念仏行から鎌倉時代の踊り念仏、江戸期の大衆化、そして2022年のユネスコ登録までを年代順に紹介し、現代における復活イベントや保存活動の最新動向も取り上げます。
行事の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 行事名 | 盆踊り(盂蘭盆会の踊り行事) |
| 目的 | 先祖供養・精霊送り/地域交流 |
| 起源 | 平安期の念仏行 → 鎌倉期の踊り念仏 |
| 発展 | 鎌倉後期に全国へ、江戸期に庶民娯楽化 |
| 近年の動向 | 2022年「風流踊」41件がユネスコ無形文化遺産登録/2024年以降各地で復活祭 |
由来と歴史(年代順)
| 年代 | 主な出来事 | ポイント |
|---|---|---|
| 10世紀 | 空也上人が鉢叩き念仏を布教 | 歩き念仏の原型 |
| 13世紀 | 一遍上人が“踊り念仏”を全国で展開 | 太鼓・鉦を打ちつつ輪になって念仏 |
| 14?15世紀 | 念仏踊り+風流(仮装・芸能)が融合 | 先祖供養と娯楽が並立 |
| 17世紀 | 江戸幕府が風紀取締りを発布 | 男女混合・夜間開催が問題視 |
| 19世紀末 | 地域独自の振付・囃子が定着 | 阿波踊り・郡上踊りなど |
| 20世紀 | 都市部では一時衰退、地方で継承 | 大正期に東京音頭登場 |
| 2020年代 | ユネスコ「風流踊」登録(2022) | 郡上、阿波、西馬音内ほか41件 |
| 2024‐25 | コロナ後の復活、渋谷・青山など都市型盆踊り盛況 | 若年層の参加増 |
現代の姿と最新トピック
- ユネスコ登録の意義
41件の盆踊り系民俗芸能が「風流踊」として世界遺産に。保存団体への助成・若手育成が活発化。 - 都市型盆踊りの復活
渋谷盆踊り(2024年再開)など、歩行者天国を利用した新スタイルが注目。 - メディアとデジタル
YouTube配信やVR体験で振付を学ぶオンライン講座が人気。 - 衣装・振付の多様化
伝統衣装と現代ファッションを組み合わせる「ネオ盆踊り」も登場。
豆知識・トリビア
- やぐらの灯りは迎え火の象徴
提灯の明かりで先祖霊を導くという民俗学的解釈がある。 - 輪になって左回りが基本
時計と逆回りは“時を戻す”=死者の国と現世の循環を意味する説。 - 江戸の取り締まり理由は「出会いの場」
若者が集まる社交の場となり、風紀を乱すとして度々禁令が出された。 - 三大盆踊り
阿波踊り(徳島)、郡上踊り(岐阜)、西馬音内盆踊り(秋田)。
まとめ
盆踊りは、念仏行という宗教的儀礼から始まり、庶民文化へと発展し、現代では世界が認める無形文化遺産となりました。
起源を知れば、櫓を囲む一歩一拍に「供養」「祈り」「交流」という多層の意味が宿っていることがわかります。
今年はぜひ地元や旅先の盆踊りに参加し、輪の中で歴史と先祖を感じてみてください。